東洋医学において、冬は「蔵(ぞう)」の季節とされ、自然界のあらゆるものが活動を控え、エネルギーを蓄える時期と考えられています。私たちの身体も例外ではなく、この季節の変化に合わせて心身を整えることが、健康維持の鍵となります。
また、臓器では冬は「腎(じん)」がもっとも影響を受けやすい季節といわれています。
腎は生命エネルギーの源とされ、冷え・疲れ・痛み・むくみ・気力の低下 などと深く関わります。
寒くなると、「体が固まる」「腰が重い」「気持ちが沈む」という方が増えるのは、
単なる冷えではなく “冬という季節そのものの影響” も大きいと考えられています。

東洋医学でいう「冬」の特徴
冬は五行では【水】に分類され、深く休む季節。
体は省エネモードになり、気血の巡りがゆっくりになります。
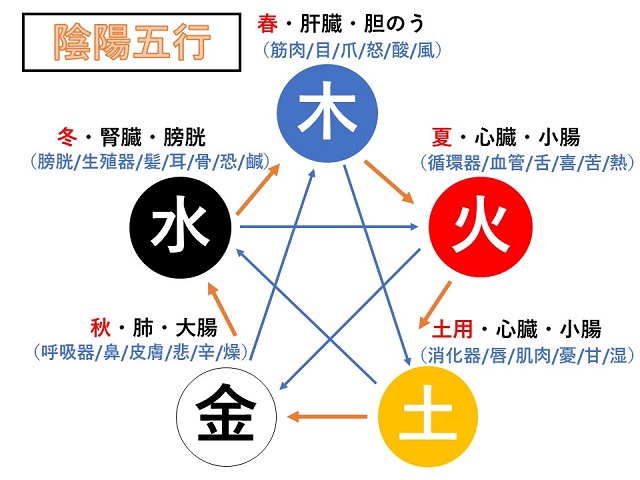
腎の働き
「腎」は以下の働きをつかさどると考えられています
- 生命力・回復力
- 水分代謝
- 腰・膝の強さ
- 耳の機能
- 尿・生殖・ホルモンバランス
- 骨の強さ
冬に多い症状
寒さにや冷えによって体の機能が停滞することにより、以下の不調が起こりやすくなります。
- 高血圧(体温を上げるために毛細血管が縮小)
- 冷えや腰痛、関節痛(寒邪による気の巡りの停滞)
- 頻尿やむくみ、膀胱炎や腎炎(腎の水分代謝機能の低下)
- 疲れやすい、気力の低下(腎に蓄えられる精の消耗)
- 耳鳴り・聴力の低下(腎と耳との関係)
- 肌や喉の乾燥(体内の水分不足や空気の乾燥)

東洋医学的な冬のセルフケア
冬は腎のエネルギーを温存し、寒邪から身体を守ることが最優先です。
温める・防寒
①腎を温める「三首(さんくび)温め」
東洋医学では首・手首・足首を温めることが腎を補う近道。
首: 風邪の侵入を防ぎます。
足首: 重要なツボが多く、下半身の冷え防止に直結します。
・ネックウォーマー
・レッグウォーマー
などを用いて冷やさない状態を保ちましょう
②下腹部(丹田)を温める
丹田(おへその少し下)を温めることで腎が補われ、気力の回復や睡眠の質UPにつながるとされます。
・腹巻
・貼るカイロ
などで対策をしましょう
③入浴
湯船にゆっくり浸かり、身体の芯から温めることが大切です。

ゆっくり深い呼吸(腎のエネルギー補充)
冷えると呼吸が浅くなり、腎の力も低下しやすくなります。
ゆっくりと深い呼吸をすると横隔膜が大きく動き、腎などの内臓に刺激が入り機能の低下を防ぎます。
深呼吸のポイント
- ③秒で吸って、②秒止めて、⑦秒で吐く
- 朝晩10回ずつ
- 背中を丸めず、胸を張って

腎を補う「黒い食材」の摂取
東洋医学では「黒は腎を補う色」。
腎を養う(補腎)とされる食材を積極的に摂りましょう。
食材例
- 黒豆
- 黒ごま
- ひじき
- きくらげ
- ごぼう
- わかめ
- こんぶ
- あずき
鍋やスープなど暖かい料理で摂るのがおすすめ。

足裏をほぐす(腎のツボ)
腎の働きを助けるツボを温めたり、軽く押したりしましょう。
・湧泉(ゆうせん)
足の裏側、土踏まずのあたりにある、足の指をグーのように曲げると、足裏にへこみができます。このくぼみが湧泉です。
・太渓(たいけい)
足の内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみにあります。
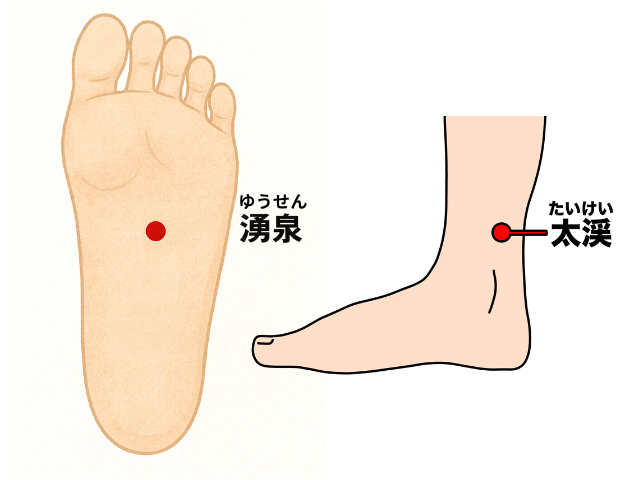
「早寝・ゆっくり過ごす」も立派な養生
東洋医学では、「冬は早寝遅起き」が良いとされています。
充分な睡眠をとり、生命エネルギーである「精」をしっかり蓄えることが、翌年の活動のための準備になります。
- 身体を無理に動かし過ぎない
- 睡眠時間はいつもより少し多め
- 大きなストレス、冷えを避ける
これらも腎を守る大切なケアとなります。

整体でできる冬のケア
整体院アクティブスイッチでは、冬の不調に合わせて
- 季節に合わせた内臓調整
- 全身の巡りを上げる施術
- 腰〜背中の緊張をゆるめる
- 呼吸が入りやすい姿勢づくり
- 冷えに強い体づくり
- 水素セラピーで、冷え・自律神経の対策
などを行い、腎の働きを整えていきます。

まとめ
東洋医学でいう冬は、体が「守りに入る季節」。
無理をすると腎に負担がかかり、
腰痛・冷え・むくみ・気力低下などが増えてしまいます。
ポイントは、「温める」「無理しない」「ゆっくり整える」。
整体とセルフケアを合わせて行うことで、冬でも快適に軽い体で過ごしましょう!

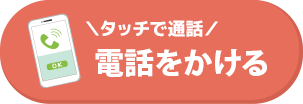






お電話ありがとうございます、
整体院アクティブスイッチでございます。